R6生物多様性に関する意識調査
問1
あなたは「生物多様性」という言葉を知っていますか。(複数選択可)
※生物多様性とは:
様々な場所で、様々な種類の生き物が、それぞれ個性とつながりを持って生きていること。
※生物多様性とは:
様々な場所で、様々な種類の生き物が、それぞれ個性とつながりを持って生きていること。
| [1] | 内容についてよく理解している (20.2%) | 35 | ||
| [2] | 意味は知らないが言葉は知っている (47.4%) | 82 | ||
| [3] | 地球温暖化と同様に重要なキーワードだと理解している (26.0%) | 45 | ||
| [4] | 生物多様性の保全活動に参加したことがある (2.9%) | 5 | ||
| [5] | 聞いたことがない (13.9%) | 24 |
問2
徳島県が平成25年10月に策定した「生物多様性とくしま戦略」を知っていますか。
※「生物多様性とくしま戦略」
生物多様性基本法第13条に基づく、
徳島県の「生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画」。
令和6年3月には、戦略の内容について2度目の改定を行ったところ。
(https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/7239234/)
※「生物多様性とくしま戦略」
生物多様性基本法第13条に基づく、
徳島県の「生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画」。
令和6年3月には、戦略の内容について2度目の改定を行ったところ。
(https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/7239234/)
| [1] | 内容についてよく知っている (2.9%) | 5 | ||
| [2] | 内容は詳しく知らないが、戦略が作成されていることは知っていた (18.6%) | 32 | ||
| [3] | 今回初めて知った (78.5%) | 135 |
問3
生態系、生物多様性の普及・保全等について、関わってみたい活動はありますか。(複数選択可)
| [1] | 希少野生生物の保護 (34.5%) | 59 | ||
| [2] | 特定外来生物、侵略的外来生物の防除 (25.7%) | 44 | ||
| [3] | 自然公園や長距離自然歩道(四国のみち)等の魅力向上 (42.7%) | 73 | ||
| [4] | 里山保全活動や森づくり活動 (33.9%) | 58 | ||
| [5] | 子供たちへの環境学習活動 (42.7%) | 73 | ||
| [6] | その他 (3.5%) | 6 |
問4
法律で指定された「特定外来生物」が増加していることを知っていますか。
※特定外来生物
海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から国が指定するもの。
飼養、栽培、保管、運搬、輸入等が規制されている。
※特定外来生物
海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から国が指定するもの。
飼養、栽培、保管、運搬、輸入等が規制されている。
| [1] | 知っている (82.7%) | 143 | ||
| [2] | 知らない (17.3%) | 30 |
問5
問4の「特定外来生物」について、対策のためにあなたができることはありますか。
| [1] | できることはない (11.0%) | 19 | ||
| [2] | 情報があれば協力できることがあると思う (48.3%) | 83 | ||
| [3] | 対策のため、外来生物について知識を得たいと思う (40.7%) | 70 |
問6
「外来種」とは、外国から侵入した生物だけでなく、国内で人為的に他地域へ移動・放出した場合も当てはまることを知っていますか。
| [1] | 知っている (65.5%) | 112 | ||
| [2] | 知らない (34.5%) | 59 |
問7
徳島県南部では県外産のオヤニラミが放流され、在来個体との交雑が進んでいます。
地域固有の遺伝子を守るため、交雑によって生まれたオヤニラミを駆除することについてどう思いますか。
※オヤニラミ
徳島県では県南の一部河川にのみ生息する淡水魚(県の「指定希少野生生物」に指定)
地域固有の遺伝子を守るため、交雑によって生まれたオヤニラミを駆除することについてどう思いますか。
※オヤニラミ
徳島県では県南の一部河川にのみ生息する淡水魚(県の「指定希少野生生物」に指定)
| [1] | 駆除に賛成 (55.2%) | 95 | ||
| [2] | 駆除に反対 (4.1%) | 7 | ||
| [3] | わからない (40.7%) | 70 |
問8
四国のツキノワグマが絶滅の危機に瀕していることを知っていますか。
※四国のツキノワグマ
「環境省レッドリスト」に「絶滅の恐れがある地域個体群」として掲載
西日本や東日本の個体群とは遺伝子タイプが異なっており、四国・紀伊半島に固有の遺伝子グループとなっている。
※四国のツキノワグマ
「環境省レッドリスト」に「絶滅の恐れがある地域個体群」として掲載
西日本や東日本の個体群とは遺伝子タイプが異なっており、四国・紀伊半島に固有の遺伝子グループとなっている。
| [1] | 知っている (73.7%) | 126 | ||
| [2] | 知らない (26.3%) | 45 |
問9
四国のツキノワグマを保護するべきだと思いますか。
| [1] | 保護するべきだと思う (56.6%) | 98 | ||
| [2] | 保護する必要はない (14.5%) | 25 | ||
| [3] | わからない (28.9%) | 50 |
ご意見・ご要望など
ご意見・ご要望などを入力してください。
| [1] | 〇徳島県が環境省の特定外来生物等一覧を徳島県民が閲覧するように普及啓発をしなければならない。 〇徳島県がお祭りの縁日の屋台で売られている特定外来生物のミドリガメの販売を禁止する。 〇徳島県が特定外来生物のハクビシンの駆除を行う。 (2.3%) |
1 |
| [2] | 「生物多様性」は非常に大事。今後の地球環境の維持の観点からも必要なことと思います。ただ、現実はなかなか複雑というか、困難なことも多いのが事実かと思います。在来種というか固有種の維持は、外来種の繁殖等もあり、その維持が脅かされているのも事実。また、在来種と外来種との交雑も進んでいる植物や動物もあり、さらに複雑になっている。農業についても、これまでの在来種は姿を消しつつあり、業者の”種”に独占されつつある現状がある。法的にも、在来種をつなぐことが困難になっている状況もある。生物多様性を言うなら、個別、生物ごとにきめ細かい対応が必要である。一律の法的な処置だけでは限界があるように思います。地元、各市町村にどんな生物があり、今どのような状況なのか、一つ一つ丁寧に洗い出す必要があるように思います。まずここからはじめるべきではないでしょうか。 (2.3%) | 1 |
| [3] | このアンケートを作られた方は生物多様性についてどれほどの知識を持って個人的にしろ仕事にしろどんな気持ちを持ってこのアンケートを出されたか、聞く機会があれば聞きたいです。 (2.3%) | 1 |
| [4] | なし (2.3%) | 1 |
| [5] | クマのためにも、他の生物のためにも、山 森林の開発は 計画中止すべきあると考えます。鳴門の大麻比古神社の上に180メートルもの風力発電をけいかくしているとのことですが、そんなことをしたら、生物多様性など 守れないように思えます。 (2.3%) | 1 |
| [6] | ツキノワグマが「問い」にあったのでこれに関連して述べると、 希少な熊が地域住民からすると害悪であったりする。 その地域で暮らさない者と暮らす者の意見で、分けて考えた方がいいかと思います。 (2.3%) |
1 |
| [7] | ツキノワグマが四国にいるなんてびっくりした。 (2.3%) |
1 |
| [8] | ツキノワグマについて、保護区があれば保護もよいかと思います。よいたとえが浮かびませんが、ニホンオオカミが絶滅寸前の時代に戻ったとしても現地で保護するべきかといえば賛成はできません。人の命にかかわるからです。 (2.3%) | 1 |
| [9] | ツキノワグマの保護も大切だとは思うが、県外のクマの被害を聞くと保護の仕方を考えるべきだと思う。 (2.3%) | 1 |
| [10] | ツキノワグマは恐いのでいなくてもいいとも思うが、やはり日本固有の生物は残さないといけないと思うので、保護した方がいいです。アメリカザリガニ、ミシシッピーアカミミガメ、アライグマ、セアカゴケグモ、クワガタなど、海外の生物がこれ以上広がらないようにしないといけないと思っていますが、触れる機会がないので、何も対策はできていません。子供たちには教えた方がいいと思います。以前県立博物館でのイベントに子供と参加して習ったのを子供は覚えています。 (2.3%) | 1 |
| [11] | ワンヘルスに生物多様性とくしま戦略は含まれますか? (2.3%) | 1 |
| [12] | 人の生活環境が変化するなかで野生の猿や猪、烏等の農産物への被害が増えています。共存できる範囲を越えた場合の対策も考える必要がありますね。 (2.3%) | 1 |
| [13] | 人を脅かしたり害を与えるのは悪いが やはり生き物だから、なるべく保護し守りたい (2.3%) |
1 |
| [14] | 人間も生物であることを充分認識しているだろうか、上から目線での意識、対策・対応が我国の現状と思える。 (2.3%) | 1 |
| [15] | 保護するしないは別として、人間が手を差し伸べ ず、自然のままに (2.3%) |
1 |
| [16] | 保護をするか否かという両極端な選択肢への回答は難しい。生態系(弱肉強食)として捉えるならば、強者の人間が生存域を広げ、弱者の動物たちが淘汰されていくのは自然の摂理。だが、昔のように共存できないのだろうか。昔は人間と動植物は、確かに境界線を設けていた。それを破ったのはもちろん人間である(過剰な繁殖・人口増加)。外来種の交雑も、人間の愚行。自己中心的で中長期的な視野を持たないがゆえの愚昧さ。もはや交雑を根絶するのは不可能であり、幼少期からの自然体系への教育が必要だが、そんなことへも注力していないように思える。脱線するが学力低下も深刻であるからだ。核家族化・家屋の欧米化が増加し、里山で暮らす子供たちも少ない。身近に自然と共に生きれば、種への感謝も生まれるはず。若人・子供たちが田舎・里山で暮らせるよう、雇用と収入の対策を。 (2.3%) | 1 |
| [17] | 全て保護していたらきりがないのでどの程度その他の生態系にも影響を与えているか考慮しなければならないと思う (2.3%) | 1 |
| [18] | 動植物の生態、人間の生活様式、自然環境、地球温暖化など、様々な要因が重なって、生物多様性にも大きな影響を及ぼしていると思います。「生物多様性」だけにとらわれず(様々な要因も含めて)、地球の未来のために、今、暮らしの中でできるちょっとしたことを、周知することは有効だと思います。 (2.3%) | 1 |
| [19] | 四国のツキノワグマは、現在絶滅しかけていると思われますが、熊は人に危害をくわえて地域によっては、かなりの死者がでており人に危害を加える動物を保護することには、何とも言えない気持ちです。人に危害を加えないような環境作りが必要だとは考えていますが、今の日本の現状ではそれは非常に困難な状況だと思います。人に危害を加えない動物も農作物に対して多大な被害を与えていることもあり、これらも保護をすることについては、大きな問題であると思っています。自然環境を今以上に悪化させることは、絶対に避けるべきですが、保護することにより人に対して危害を加えられたり、生活環境を侵されることに対しても何らかの手を打たないといけないのではないかと思っています。 (2.3%) | 1 |
| [20] | 地域固有の遺伝子を守るために、人の手によって放流され命を育んでいる物を駆除するのは、どこか違うような気がする。 四国のツキノワグマが住みやすい環境整備をして欲しい。 (2.3%) |
1 |
| [21] | 外来生物により在来の生き物が少なくなっていることに加えて、ネオニコチノイド系殺虫剤やその類似農薬についても考える場があると良いと思う (2.3%) | 1 |
| [22] | 外来種の駆除はいったん混ざってしまうと難しいとおもいます。 (2.3%) | 1 |
| [23] | 外来種はアメリカザリガニ、絶滅危惧種はコウノトリが指定されていると知っていたが、オヤニラミやツキノワグマも指定されているうえに身近にいる存在であったことは知らなかった。生物多様性について広報し、学習の機会を設けることが必要と思う。実際に外来種の捕獲作業や絶滅危惧種の観察など体験型活動も効果的だと思う。 (2.3%) | 1 |
| [24] | 情報等で知っていても、自分が行動出来る事は少ないと思う。出来る範囲で協力出来ればと思う。 (2.3%) | 1 |
| [25] | 日本古来の在来種を保護することには、賛成です。 反論の余地はありません。 しかし、『外来種を見つけたら、即駆除』という考え方や、 駆除するべきだという考え方に、強い違和感を覚えます。 県民の理解度が薄いままに、言葉だけを広めることは 間違っています。 (2.3%) |
1 |
| [26] | 普段考えることのない内容なので回答者として意識向上に繋がっていると思う。 (2.3%) | 1 |
| [27] | 東北や北海道でツキノワグマの被害があるので、ツキノワグマの保護については少し疑問がある。 (2.3%) | 1 |
| [28] | 東日本の居住区への熊出没のニュースに危険で怖いなと思ったり、四国では熊は絶滅危惧種だったりして熊に対する印象が地域で変わってくるのだろうなと想像しています。お互いの地域の事情を知らないと誤解等もありそう。そういった面での理解を深めることも「生物多様性」に繋がるのかなと考えながらアンケートに答えました。 (2.3%) | 1 |
| [29] | 毎年剣山が好きで行っていたが 近年足腰が痛くあまり行けなくなった。 次世代へ剣山の環境を残し、つなぐためにできることがあれば 協力したいと思っている。 (2.3%) |
1 |
| [30] | 無し。 (2.3%) | 1 |
| [31] | 特になし (2.3%) | 1 |
| [32] | 特定外来生物にはどのような物があるのか、どのような処理、処分をすればよいのかがわかるように周知してほしい。知識を得ることで不特定多数の人が対応できることは多いと思う。例えば学校での出前授業や配布資料であれば子供達へ、更には家族へ伝わると思う。各企業や公民館、コミセンなどを利用する団体へ直接資料を配布したりしても大人に周知されると思う。リーフレットを施設の置くだけなどでは興味のある人しか手に取らないので意味がないと思う。 (2.3%) | 1 |
| [33] | 理学部生物学科卒で、研究員をしていたので、今回のアンケートはぴったり?です。忘れかけていますが・・・一般のおばさんよりは、知識あります。問9は、特に昔から難しい事で簡単に答えは見つかりません。 (2.3%) | 1 |
| [34] | 生物が苦手なので、今回のアンケートは消極的な回答になってしまいました。申し訳ございません。 (2.3%) | 1 |
| [35] | 生物の多様性保護は、専門機関との連携が必要だと考えています。 子供たちに自然環境を保全することは大切な人権保護活動だと思っています。 啓発活動を進めるとともにスタッフを育成し若者たちが自ら活動できる環境を作ることを同時に進める事が肝心だと思っています。 (2.3%) |
1 |
| [36] | 生物多様性に関する事を徳島県公式ホームページ、県政だよりOUR徳島、徳島県テレビ広報番組「とくしまタイムズ」、徳島県ラジオ広報番組「ラジオOUR徳島」、「エフエムOUR徳島」、「県からのお知らせ」で知らせるべきである。 (2.3%) | 1 |
| [37] | 生物多様性はまだまだ認知が低いと感じています。知っていただく活動に取り組んでいますが、気候変動の理解よりも分かりにくいと思われます、官民一体となってたゆまずに推進していくことが大切だと考えられます。いなくなってしまっていい生物などはいませんし、現状の課題に目を向けて生物多様性の向上に努めていきたいと日頃から考えています。 (2.3%) | 1 |
| [38] | 絶滅の恐れがある生物は難しいとは思うが保護できるといいと思う (2.3%) | 1 |
| [39] | 絶滅危惧種と言っても残すべき動物なら守るべきです。 が、被害や危害だけならどうかと思います。 ジビエ料理として活かせるなら捕獲するのもいいと思います。 (2.3%) |
1 |
| [40] | 身近な話題と認識されるよう多方面で情報発信をお願い致します。 (2.3%) | 1 |
| [41] | 農作物などに影響があることに危惧しています。対策をよろしくお願いします。 (2.3%) | 1 |
| [42] | 過去に県内では、タップミノーが蚊の幼虫ボウフラの駆除を目的に放流され効果をあげたと大きく報道されたが、その後の報道は全く無かとった。今回のアンケートで改めて調べると、タップミノーは「カダヤシ(特定外来生物)」であることを初めて知った。報道されない理由も理解した。しかし、ボウフラの駆除に効果があったことも事実で少し複雑な気持ちもある… (2.3%) | 1 |
| [43] | 1.自分の生活が自然環境が大きく影響している水や食料に支えられている事と、相応の努力や配慮がなければそれらを維持できないことを理解し共有する努力が必要。 2.気候変動も環境の問題も視野を広げて、世界中で発生している事にもっと敏感になるべきで、また諦めたらダメな事であることも認識したい。 3.人口減少社会で生物多様性に関する活動をするために県民市民企業のネットワークを強化していくべきで、環境県民会議を活用してほしい。 4.エコみらいとくしまは、もっと真面目に仕事をしてほしい。 (2.3%) |
1 |
年齢別
| [1] | 20歳未満 (5.8%) | 10 | ||
| [2] | 20~29歳 (10.4%) | 18 | ||
| [3] | 30~39歳 (12.1%) | 21 | ||
| [4] | 40~49歳 (24.3%) | 42 | ||
| [5] | 50~59歳 (22.0%) | 38 | ||
| [6] | 60~69歳 (13.9%) | 24 | ||
| [7] | 70歳以上 (11.6%) | 20 |
職業別
| [1] | パート (2.9%) | 5 | ||
| [2] | 派遣社員 (0.6%) | 1 | ||
| [3] | 無職 (8.1%) | 14 | ||
| [4] | 看護師 (0.6%) | 1 | ||
| [5] | 社協職員 (1.2%) | 2 | ||
| [6] | 自営業 (1.7%) | 3 | ||
| [7] | 販売業 (0.6%) | 1 | ||
| [8] | 農業 (0.6%) | 1 | ||
| [9] | 農林漁業 (0.6%) | 1 | ||
| [10] | 農林漁業以外の自営業 (1.7%) | 3 | ||
| [11] | 会社員 (33.5%) | 58 | ||
| [12] | 団体職員 (5.8%) | 10 | ||
| [13] | 主婦 (12.7%) | 22 | ||
| [14] | 学生 (7.5%) | 13 | ||
| [15] | その他 (22.0%) | 38 |
住所別
| [1] | 徳島市 (34.1%) | 59 | ||
| [2] | 鳴門市 (5.2%) | 9 | ||
| [3] | 小松島市 (6.9%) | 12 | ||
| [4] | 阿南市 (6.9%) | 12 | ||
| [5] | 吉野川市 (3.5%) | 6 | ||
| [6] | 阿波市 (4.6%) | 8 | ||
| [7] | 美馬市 (2.9%) | 5 | ||
| [8] | 三好市 (2.3%) | 4 | ||
| [9] | 勝浦町 (1.2%) | 2 | ||
| [10] | 上勝町 (0.6%) | 1 | ||
| [11] | 佐那河内村 (1.2%) | 2 | ||
| [12] | 石井町 (5.8%) | 10 | ||
| [13] | 神山町 (1.2%) | 2 | ||
| [14] | 那賀町 (0.6%) | 1 | ||
| [15] | 牟岐町 (1.2%) | 2 | ||
| [16] | 美波町 (1.2%) | 2 | ||
| [17] | 海陽町 (1.2%) | 2 | ||
| [18] | 松茂町 (1.7%) | 3 | ||
| [19] | 北島町 (2.9%) | 5 | ||
| [20] | 藍住町 (6.4%) | 11 | ||
| [21] | 板野町 (4.0%) | 7 | ||
| [22] | 上板町 (2.3%) | 4 | ||
| [23] | つるぎ町 (1.2%) | 2 | ||
| [24] | 東みよし町 (1.2%) | 2 |
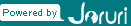
今回のアンケートは、県民の皆様の生物多様性を目
的として実施いたしました。ご協力いただいた
皆様、ありがとうございました。
1 調査期間 令和6年7月25日~8月7日
2 調査対象 オープンとくしまe-モニター
200名
3 回答状況 回答者数 173名
回答率 86.5% )